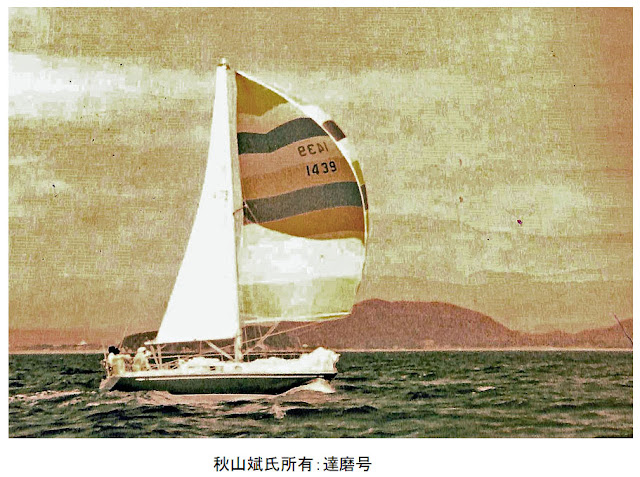2025年7月7日月曜日
2025年7月6日日曜日
2025年7月5日土曜日
2025年7月4日金曜日
2025年7月3日木曜日
スカンジナビア号が「ふね遺産」に 日本船舶海洋工学会が認定 【沼朝令和7年7月3日(木)号】
スカンジナビア号が「ふね遺産」に
日本船舶海洋工学会が認定
日本船舶海洋工学会は、歴史的で学術的・技術的に価値のある船舟類および、その関連設備を文化的遺産として次世代に伝えようと「ふね遺産」に認定しているが、今年で9回目を迎える認定審査がこのほど行われ、6月16日付で非現存船ながら、スカンジナビア号が認定された。
スカンジナビア号はディーゼルエンジンを搭載したモーターシップで、クルーズ客船「ステラ・ポラリス」として1926年にスウェーデンで建造された。以来、世界の海で活躍し、40年にナチスドイツに接収されて軍事利用されたが、46年にスウェーデンに戻りクルーズ船に復帰。70年に日本の企業に売却された。以来、西浦木負に係留され、フローティングホテル・スカンジナビアとして営業。長年、市民に親しまれ、その後レストラン事業に業態を変更したが、業績の悪化で2005年に営業を終了した。
その後、地域住民らが中心となって「スカンジナビアを保存する会」を立ち上げ、保存を訴える活動も行われたが、06年にスウェーデン企業への売却が決まり、8月31日にタグボートに引かれて木負を出航。上海に寄港して改修し、スウェーデンに向かう予定だったが、9月2日、和歌山県沖で沈没した。
木負のカフェ&ランチ海のステージ店主の前島希久也さんは、スカンジナビア元船長(支配人)の故安楽博忠氏から譲り受けたステラ・ポラリスの航海日誌など縁の品、思い出の品を集め、スカンジ一ナビア号資料館を店内に設けて一般公開。「伝説は今も生き続けている」と、来賓も招いてスカンジナビア号の思い出や伝説を語り継ぐイベントを定期的に開いている。
同学会による「ふね遺産」の認定は53号目で、非現存船では第13号。スカンジナビア号はヨーロッパのロイヤル・ヨットの伝統をよく伝える秀麗なクルーズ船とされ、日本初のフローティングホテル・レストランとしてレジャー産業の創設と地域振興に多大な貢献を果たしたことや、世界的にも貴重な船舶海洋文化遺産として、地域住民による自発的な保存運動を呼び起こし、現在も、その活動が続けられていることなどが評価された。
認定書及び認定プ一レートは9月ごろ、海のステージに贈呈される予定。
前島さんは「協力してくれた皆さんのおかげでスカンジナビア号が、『ふね遺産』に認定された。認定証が届いたら資料館に展示し、今後も講演会などのイベントを企画していきたい」と喜んでいる。
5月にはスカンジナビア号の講演会
和歌山沖に沈む今の姿捉えた映像も
一方、5月にはスカンジナビア号資料館と実行委員会の共催により、トークイベント「スカンジナビア号の物語~歴史を刻んだ船、そして海底への旅」を三津の内浦地区センターで開き、約160人が参加した。
講師4人による講演が行われ、はじめに信州大学名誉教授の伊藤稔さんが「スカンジナビア号の歴史と功績」をテーマに話し、続いて沼津史談会の長谷川徹副会長が「船と歩んだ沼津の歴史」をテーマに、スカンジナビアが木負に係留される前の沼津のまちなかの様子、その後の変遷を話した。
次に、清水町サ≧トムーン柿田川3階、幼魚水族館の館長で岸壁幼魚採集家の鈴木香里武さんが「少年時代のスカンジナビア号との想い出」と題して講演した。 鈴木さんは4歳の頃から毎年、スカンジナビア号に家族で宿泊し、近くの岸壁で初めて小さな魚を採取し、「現在の活動の原点になった」と言い、30年程前の当時ホテルだったスカンジナビア号の船内や客室の様子を映した。
また、小さな体で大海原を生き抜く幼魚の魅力を紹介し、「幼少期の体験は大事で、スカンジナビア号に泊まったことで今の自分がある」と話した。
最後に(ダイビングショップを開くスティングレイ・ジャパン代表の野村昌司さんが「海の底で静かに鼓動するスカンジナビア号の今」と題し、和歌山県沖の水深70㍍余の海底に沈むスカンジナビア号を撮影した動画を公開した。
野村さんは36年間に8000回以上ダイビングし、最深122㍍まで潜るテクニカルダイパi。1人当たりタンク5本、総重量100㌔超えの重装備で潜水チームを組んでスカンジナビア号の現状を記録し、沈没から約20年後の現在の姿を捉えた。
この潜水は5月に9日間の日程で行ったが、風や潮の流れの影響で潜れたのは3日間。砂地に全長約130㍍の船体が沈み、「1㍍のヒラメ、人間程の大きさのサンゴなど、生物のすみかになっていた。今まで、いろんな場所に潜ったが、これだけたくさんの生物が見られたのは初めて」だと言う。
船体中央の煙突、一船内の壁は崩れ、船首のマストは折れていたが、後方のマストは残っており、丈夫な造りだったことをうかがわせた。中央のスイートルーム、メーンダイニングなどの映像が当時の面影を偲ばせた。
野村さんは「スカンジナビア号には強い思い入れはなかったが、実際に潜り、皆さんの話を聴く中で、変化していく姿を、できる限り記録として残したいと思った。潜れるダイバーも限られるので、(記録として残すのは)我々の使命だと感じる」と話した。
終わりに前島さんが「かつてスカンジナビア号は、あって当たり前だったが、無くなって寂しく思う。最後の船長だった安楽支配人から預かった伝統を、これからも資料館で伝えていきたい」と語った。
【沼朝令和7年7月3日(木)号】
2025年7月2日水曜日
2025年7月1日火曜日
沼津兵学校情報案内板設置を史談会、 シンポで提案 【静新令和7年7月1日(火)朝刊】
沼津兵学校情報案内板設置を史談会、
シンポで提案
沼津郷土史研究談話会(沼津史談会)は29日、城下町としての沼津を学ぶ「歴史遺産シンポジウム」を沼津市立図書館で開いた。沼津兵学校に関する情報案内板を中心市街地に設置するなど、歴史を次世代に継承していくためのまちづくりを提案した。
史談会の匂坂信吾会長は情報案内板の設置のほか、沼津城の名残がある沼津中央公園(同市大手町)の東側にあったとされる「二重櫓(やぐら)」の木造再建を提案。「沼津駅の開設以降、沼津城、沼津兵学校などの面影がみるみるうちになくなった。歴史の継承と文化発展に役立つはず」と強調した。
市中心市街地まちづくり戦略会議の福井恒明委員(法政大教授)は「案内板の設置は現代までのまちづくりの様子を入れたら良いかも」とアドバイスし、来賓の頼重秀一市長は「歴史的背景や文化財を活用したまちづくりを連携して進めていければ」と応じた。
【静新令和7年7月1日(火)朝刊】
2025年6月28日土曜日
2025年6月27日金曜日
沼津駅南口の西武跡地 飲食店や広場整備へ 市、URと民間4社 (静新記事)沼津駅前にぎわい広場 事業者決まり来秋開業目指す (沼朝記事)
沼津駅南口の西武跡地
飲食店や広場整備へ
市、URと民間4社
沼津市は26日、都市再生機構(UR)と進めるJR沼津駅南口の旧西武沼津店本館跡地の活用について、新たな民間事業パートナーとして不動産開発の「フィル・カンパニー」(東京)を代表とする企業グループを選定したと発表した。飲食店などの入居を想定する2階建ての建物や芝生広場などを整備し、2026年秋の開業を指す。市は沼津駅の鉄道高架化に向けた段階的な「まちの変化」の象徴として位置づける。
企業グループは他に設計会社のフィル・コンストラクション(東京)、デザイン会社のブルースタジオ(同)、加和太建設(三島市)の3社で構成。「緑あふれる暮らしの舞台」をテーマに民間企業と市が831平万㍍の敷地に延べ床面積約580平万㍍の建物を建て、飲食や小売などのテナントを誘致する。
市も約1億円をかけて、イベント会場としても使える芝生広場やキッチンカーの利用を想定したスペースなどを整備し、民間施設との合築で公衆トイレやまちづくり活動の拠点を設ける。
高架完成時の駅前再整備も踏まえ、事業期問は46年3月までの約20年間。頼重秀一市長は「鐵道高架は41度までと長期の事業。段階を経てまちが変わったか感じ機会になる」と期待した。
旧西武沼津店が2013年に閉店後、跡地ではアニメ「ラブライプ!サンシャ一インー-"」の公式カフェやレンタカー店が24年2月まで営業していた。市とURが民間事業者を一時募集したが不調に終わり、今年3月から再募集していた。
(東部総局・尾藤旭)
【静新令和7年(2025年)6月27日(金曜日)】
沼津駅前にぎわい広場
事業者決まり来秋開業目指す
沼津駅南口の西武百貨店沼津店本館跡地に整備を予定している、にぎわい拠点の事業パートナーが決定し、来秋開業に向けて動き出した。26日に開かれた定例記者会見で頼重秀一市長が発表した。
西武沼津店は2013年に閉店し、本館は解体されて831平方㍍の更地となソ、所有する伊豆箱根鉄道が暫定活用として、沼津駅前のにぎわい創出のための「沼津駅前にぎわい広場」を運営し、日産レンタカーと雄大の飲食店が出店した。17年にマンションデベロッパーに土地が売却されたが、「駅周辺オープン化」に向けて独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が土地を取得。昨年2月に雄大が契約満了に伴い閉店後は更地になっていた。
市は、カフェや店舗を有する拠点施設と、自由に使える芝生広場からなる「実践広場」の整備に向けて昨年度、民間の事業パートナーを募集したが、工事費の高騰などを理由に応募がなかったため条件を見直すとともに、同所を中心に、公共空間活用の社会実験「オープンヌマヅ」を2回実施。
改めて事業パートナーを募集し、狭小地や変形地の暫定活用を得意とするフィル・カンパニーを代表企業に、商業ビルの設計・施工を行うグループ会社のフィル・コンストラクション、広場の設計等を手掛けるブルースタジオ、三島市の加和太建設の3社と共に構成するグループが今月25日、市、URとパートナー協定を締結した。
にぎわい拠点のコンセプトは「暮らしの表現者たち集う緑あふれる暮らしの舞台」。建物は鉄骨2階建てで、建築面積400平方㍍、延べ床面積580平方㍍で、北側の地域貢献部と、南側の店舗部で構成。
市が維持管理する地域貢献部と西側の広場部は市が主体なって整備し、事業費は約1億円。地域貢献部1階には公衆トイレと倉庫、2階は市民の活動拠点として貸し出し、アート展示やワークショップ、セミナーの開催、試験的に出店するポップアップストアとして活用する。
2階に上がる階段を立体的に構成し、座れる居場所、演奏会の観客席としても機能する階段広場として整備し、芝生広場には低・中木の植栽帯を設け、木々に囲まれた緑地空間を計画している。
事業者グループが整備する店舗部は、1階と2階にテナントを設け、エレベーターを整備。1階の一部はピロティで全天候型広場となり、キッチンカーの受け入れも想定する。
7月中に測量と地盤調査を行い、8月から設計、12月ごろに工事着手。来秋の供用開始を目指し、事業期間は鉄道高架事業が終了するまでの20年間が考えられている。
頼重市長は「これまでの車中心の社会からヒト中心のまちづくりに転換するための拠点施設。中央公園の整備や狩野川かわまちづくり計画などと連携し、中心市街地活性化のための様々な取り組みを進めたい」と話した。
【沼朝令和7年6月27日(金)号】
2025年6月26日木曜日
2025年6月25日水曜日
2025年6月24日火曜日
市民歴史講座 「遺跡・史料の語る沼津の古代史」 高 尾 山 古 墳 を 守 る 会
市民歴史講座 「遺跡・史料の語る沼津の古代史」
(写真…休場遺跡 石囲い炉)
2025年度第1回(通算19回)
「謎が拡がる日本旧石器時代」
これから5回に渡り、旧石器時代から古代国家の形成まで、改めて時代ごとに大まかに歴史
の流れをたどる講座を行います。専門的な研究の発表や紹介というよりも、初歩的な歴史の発展を学び直そうという趣旨です。気楽に講座にご参加ください。
第1回は、人々が日本列島に渡ってきた時代、旧石器時代です。
先頃、広島冠遺跡で約42000年前の石器が発見され、現生人類の日本列島への渡来や広がりに謎や関心が高まっています。
愛鷹山南東麓でも、およそ38000年前頃から人々が生活を営み、井出丸山遺跡や、国指定史跡の休場遺跡など、その痕跡が残されています。
旧石器時代の人々の広がりや暮らしぶりなど改めて学んでみませんか。
講師 笹原 芳郎先生(静岡県考古学会会員)
開催日 2025年 6
月29日(日)13:30-16:00
(開場13:00)
会場 金岡地区センター大会議室 (沼津市江原町3-1)
資料代 300円
高 尾 山 古 墳 を 守 る 会 HP http://takaosankofun.g1.xrea.com/ 事務局 〒410-0018 沼津市豊町5-3 江藤 幹夫 ℡ 055-923-3877 E-mail xd857322@cg8.so-net.ne.jp
歴史遺産の再現 匂坂信吾 【沼朝 令和7年6月24日(火)「言いたいほうだい」】
歴史遺産の再現 匂坂信吾
今月二十九日(日)午後二時から、沼津市立図書館視聴覚ホールで沼津郷土史研究談話会(沼津史談会)総会記念「歴史遺産シンポジウム」を開催します。
最初の講演は、国立歴史民俗博物館の樋口雄彦教授による(仮題)「沼津兵学校と静岡学問所」であり、德川家が設けた二つの教育機関の比較から、当時の我が国における最先端学術都市の地域を形成した歴史を学びます。
樋口さんは皆様ご承知の通り、沼津市明治史料館の初代学芸員として十七年間在籍して、江原素六と沼津兵学校を基本テーマとして取組んできました。
次の講演は、名古屋市立大学の鵜飼宏成教授による(仮題)「沼津城址を生かしたまちづくりのために」で、経済学の立場からまちづくりの方向を探ります。
鵜飼さんは法政大学元総長の故・清成忠男先生の門下で、学生時代には清成ゼミの合宿で度々沼津を訪れ、現在は起業指導や地域活性化に取組んでいます。
講演の後はシンポジウムのテーマ「沼津まちなかの歴史遺産を創ろう」に関連して、本会から画像と解説、提案による問題提起を行います。
画像は改定中の沼津まちなか歴史MAP、沼津城絵図などに加え、参考事例として鵜飼さんと共に訪問した、愛知県西尾市の歴史公園内に民間主導で再建中の西尾城・施設配置図や二重櫓の写真です。
提案の一点目は、沼津兵学校の校舎として使用した沼津城二の丸御殿があった大手町中心部に、民間の力で早期に沼津兵学校の案内板を設置することです。
二点目は、明治初期まで沼津城本丸に存在した二重櫓を、実際の立地場所が空地となっている大手町の中央公園内に再建して、歴史学習や観光案内などに活用することが、歴史を生かした沼津のまちづくりのために重要と考えます。
このため市民や関係団体・企業などの賛同を求め、市行政の全面的な支援をいただく中で可能な限り十年以内に再現できるよう、〝沼津に城があったころ再現実行委員会〟の成果を踏まえ、新たに活動を始める所存です。
そして最後は、参加者の間で提案についての意見交換を行う予定です。
会場の定員は二百人ですが、参加者のうち希望者には会議終了後、昨年発行した会誌『沼津史談』75号(沼津城址まちづくり特集。沼津藩水野家への新たな評価や詳細な家系図を掲載)を進呈します。
参加申込み・問合せは次まで。①沼津史談会副会長、よろず相談所主人・長谷川徹☏090—1273—3774、②同、ぬまづ観光ボランティアガイド会長・上柳晴美☏090—1418—3723
(小諏訪、沼津史談会会長)